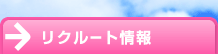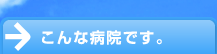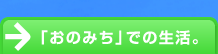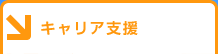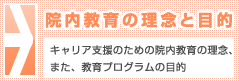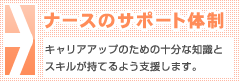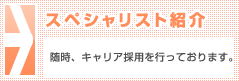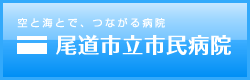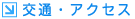- キャリア支援
- エキスパートナース/スペシャリスト紹介
当院ではスペシャリストが活動し、看護の質向上に貢献しています。また、資格取得と活動を支援しております。

精神看護専門看護師
精神的なことで、Cこまったときは・Nなんでも・S相談(CNS)
-
堤 一樹 KAZUKI TSUTSUMI
精神看護専門看護師には、総合病院などで心のケアを行うリエゾン精神看護の領域があります。リエゾンとはつなぐ、連携するという意味のフランス語で、リエゾン精神看護とは、精神看護の知識と技術を用いて心と身体を繋ぐことにより、身体疾患をもつ患者さんが抱える精神的な問題や課題に対応する看護領域になります。特に当院は急性期病院でもあり、突然の入院などでは患者さんの抱える精神的、心理的負担などは大きいものです。さらに、近年では日本の社会は高齢化が進んでおり、認知症やせん妄の患者さんも居られます。これらの負担を感じている部分、心の負担を抱えている患者さんやせん妄を合併している患者さんに対して介入し、医療スタッフ全体で、少しでもその人らしく生活が送れるように支援していくのが特徴となります。
当院において、心の問題やせん妄患者さんの看護提供を行い、患者さんやご家族のみならず、医療スタッフの困っているということを少しでも減らし、心の負担を減らしエンパワメントできるよう活動を行っていきます。
皮膚・排泄ケア認定看護師
実践・指導・相談で看護ケアに貢献
-
安保 苗美 NAEMI ABO
認定看護師とは、看護現場において実践・指導・相談の3つの役割を果たす事により、看護ケアの広がりと質の向上を図ることに貢献します。
皮膚・排泄ケア分野は主に、ストーマ(人工肛門)造設・褥瘡(床ずれ)等の創傷及び尿や便失禁に関する事で大きな役割は皮膚障害の予防とスキンケアです。この領域で皮膚障害を抱える患者さんに対して問題点を把握し、適切なケアを提供しています。正しいケアを行う事で確実に皮膚障害が目に見えて改善する分かりやすい領域です。現在、月に2回ストーマ外来を行い、入院および外来の患者さんやご家族の方が今までと変わらない日常生活を安心して送れるようストーマケアの指導や相談に応じています。
そして、院内で皮膚トラブルの相談依頼があった時には早急に対処し皮膚障害が悪化しないように心がけています。
今後は医療スタッフ全員が、患者さんの抱える問題点を抽出し解決していけるようになるため院内研修会を行い、スタッフの知識普及、技術向上に努めていきたいと思います。そして病院だけでなく、市民の皆様の健康にも貢献していきたいと思っています。お気軽にご相談ください。
-
弓手 倫恵 MICHIE YUMITE
私は当院で二人目の皮膚・排泄ケア認定看護師です。現在、二人の皮膚・排泄ケア認定看護師と一緒に、褥瘡のケアやストーマ外来、難治性創傷のケアなどを行っています。
高齢化、長寿命化、老々介護。そういった状況の中、病院は病床数の削減、入院期間の短縮を目指さねばならず、自宅や施設で過ごす寝たきりの患者さんは増えつつあります。褥瘡は寝たきりの患者さんに発生しやすく、一度できると再発しやすい傷です。褥瘡を予防するためのマットを導入し、予防ケアについての研修を行い、全ての看護師が褥瘡の予防に力を注いでいますが、褥瘡をゼロにすることはなかなかできません。また、自宅でできた褥瘡を当院で治療しても、退院すると再発、悪化する。そんなケースもあります。褥瘡の予防と治療は、医療従事者だけではなく、患者さんに関わる全ての人たちの協力が必要です。私たち皮膚・排泄ケア認定看護師は、当院に入院している患者さんだけでなく、他施設や自宅で過ごしている全ての人たちの褥瘡予防と治療に貢献します。そのために今後も研鑽を重ね、より良いケアを追究していきます。
-
光谷 真穂 MAHO MITSUTANI
私は外科・消化器内科の混合病棟に所属し、2名の皮膚・排泄ケア認定看護師と共に活動しています。創傷ケアでは褥瘡などのケアや予防方法を提案し、ストーマケアではケアの指導や患者さんに適した装具の選択、精神的サポートを行います。
中でも、特に私は排泄ケアに深く取り組んでいます。排泄というごく当たり前の行為が、もしできなくなったらどうでしょうか。私たちは、たとえトイレで排泄できなくても、パッドやおむつを使用していても「気持ち良く排泄できる」よう支援していきます。
頻尿や失禁で悩んだり、おむつやパッドを使用されている患者さんは少なくありません。排泄に関わる悩みは非常にデリケートで相談しにくいと感じる方も多く、排泄行為が満足にできないことは自尊心を傷つけ、生活の質の低下や社会的孤立に繋がる危険性があります。だからこそ、排泄に関して問題を抱える患者さんやご家族の思いに寄り添い、入院中も退院してからもその人らしく生活できるように支援していきたいと考えています。そのためには、患者さんやご家族にとって、気軽に相談できる身近な存在でありたいです。そして、入院中だけでなく、退院後の在宅や他施設・他院とも連携し、より良い排泄ケアを提供できるよう、活動の幅を広げていきたいです。
感染管理認定看護師
感染対策の合言葉は、持ち込まない!持ち出さない!広げない!
-
内海 友美 TOMOMI UTSUMI
感染管理の目的は、医療を提供する場で働くあらゆる人々及び患者さんとそのご家族を感染から守ることです。その中で感染管理認定看護師は、疫学の知識に基づく医療関連感染サーベイランスを実践し、ケア改善にむけた感染防止技術の指導や多職種と連携し問題解決に向けた相談・調整等を行う役割があります。
私は「持ち込まない・持ち出さない・広げない」を感染対策の合言葉に、当院にあった医療関連感染の予防と管理システムを構築し実践するために、感染防止対策チーム(Infection Control Team:ICT)への報告体制を整え、院内の情報を早期に把握し対応出来るようにしています。また、院内ラウンドやコンサルテーションを通じて感染防止対策が実践されているか、臨床現場で困っている事はなにか等を把握し、ICTメンバーやリンクスタッフとともに改善策の立案や評価を行っています。
当院ではキャリアサポートとして、認定看護師の資格取得や活動に対して看護部をはじめ病院全体の理解と支援があるため、日々やりがいと充実感を感じています。
-
代畑 光教 MITSUNORI DAIBATAKE
感染管理認定看護師は、患者さんとそのご家族、そして病院職員を含む、全ての人々を感染から守る役割があります。
主な内容は外来や病棟で行う感染防止対策の実際について、患者さんやそのご家族、病院職員に対して指導や相談を行っています。
感染症は治療することよりも予防することが重要になります。病院に入院される患者さんは健康な方に比べ、免疫が正常に機能しなくなる、医療器具を長期間使用するなどの理由により、様々な感染症にかかりやすくなります。
スタッフとともに感染症の予防活動を行うことで、入院患者さんの治療がスムーズに進められるよう支援していきたいと思います。
集中ケア認定看護師
重症患者さんの回復と未来をサポートする
-
山本 昌弘 MASAHIRO YAMAMOTO
集中ケア認定看護師は、重篤な患者さんの症状や状態の変化を読み取り、適切なケアを行うことで、重篤化や身体機能の低下などの二次的合併症を予防する役割があります。
私は、重篤な患者さんやそのご家族に寄り添うケアを実践し、より安楽に安心して入院生活を送ることができるような看護を提供していきたいと思っています。
また、医療スタッフと共に、体位調整やリハビリテーションなどの早期回復への援助を実践し、患者さん一人一人に応じた自立や生活の質の維持・向上に努めていきたいと思っています。
-
檀上 恵美子 EMIKO DANJO
急性期における看護ケアは患者さんの予後を大きく左右すると考えます。私は、日々、ベッドサイドでの看護実践を通してスタッフと共に考えながら、根拠に基づいた看護ケアの提供につなげていき、看護の質の向上と一貫した看護ケアの継続ができるように取り組みたいと考えています。そして、患者さんおよびご家族が安心して治療を受けられるように努めたいと思います。
緩和ケア認定看護師
緩和ケアの基本は「Not doing,but being(何かをするのではなく、ただそばにいること)」
-
黒河 香織 KAORI KUROKAWA
緩和ケア=がん患者さんへのケアというイメージがあると思いますが、慢性心不全、COPDなどの呼吸器疾患、終末期の腎不全、神経難病、認知症などのがん以外の疾患もケアの対象としています。また、終末期だけではなく、病気の診断時や治療早期の心理面の支援などを含めていつでも提供されるものです。
私は2011年に緩和ケア認定看護師の資格を取得し、外来化学療法室に所属しています。また、緩和ケアチームの一員として、多職種カンファレンスや病棟ラウンドを行っています。患者さんとご家族が、その人らしい生活を送ることができるよう、からだと心の辛さを和らげるお手伝いをさせていただきます。
救急看護認定看護師
救急看護の3S「speed(迅速),safety(安全),smile(笑顔)」
-
江木 美峰 MIHO EGI
救急看護とは『病院の内外を問わずあらゆる場面で生じる患者さんへの救急処置が必要となる状況において、実践される看護活動』です。限られた時間と少ない情報からアセスメントを行い、緊急度・重症度の判断を行います。
全身状態の急激な変化や危機的状況下にある患者さんに対して、問題の優先順位を判断し、適切な初期対応を行います。
私は最新の知識と熟練した技術の研鑽に努め、救急に関わる様々な職種の方々と連携・協働を図りながら患者さん及びご家族へ、より質の高い看護が提供できるよう努めていきます。
慢性心不全看護認定看護師
心臓を大切に.人生を豊に.
-
正木 未来 MIKI MASAKI
心不全とは心筋梗塞や弁膜症などで心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり生命を縮める病気です。日本では心疾患は悪性新生物(がん)についで死亡原因の2位となっており、高齢化が進み心不全患者さんも増加傾向にあります。
心不全の発症・増悪を予防するためには食事や運動などの生活調整がとても重要になります。しかしこれまで過ごしてきた生活を変えることは容易なことではありません。また高齢心不全患者さんは老化に伴う身体機能や認知機能の低下で生活調整がうまくできず入退院を繰り返す方が増えています。
私は2013年に慢性心不全看護認定看護師の資格を取得しました。現在は心不全患者さんに対し多職種のスタッフと協働しながら療養支援を行っています。また定期的な情報発信や患者さんやそのご家族・地域の介護職の方からの相談業務、当院の看護職種や近隣の病院・施設などで心不全の研修会を実施し心不全患者さんへの支援の輪を広げています。
「心不全患者さんの苦痛や不安を少しでも軽減し、患者さんらしさを大切に地域で生活をできる」ことを目指して、これからも尽力していきたいと思います。
認知症看護認定看護師
「認知症と共に生きる」を支える
-
田邊 直人 NAOTO TANABE
我が国において、アルツハイマー型認知症をはじめレビー小体型認知症など、認知症を患う人の増加は大きな社会問題となっています。
多くの認知症は発症から終末まで様々な過程を経て、ゆっくりと進行していきます。たとえ認知症になってもその人らしく、できる限り健やかに過ごせるように支援することが社会的に求められています。
認知症看護認定看護師として、認知症のある人の状態を統合的にアセスメントして本人が出来ることの支援や、ご家族のサポートが出来るように、認知症のある人を中心としたご家族、保健・社会福祉制度、医療スタッフとの連携・協働体制を作る必要があると考えています。
病院内に限らず、在宅でも認知症のある人への関わりに悩むご家族や医療スタッフは少なくありません。支援される人と、支援する人の双方の“想いが伝わる”ケアの実践が出来るように日々悩み、多くのスタッフと協力しながら取り組んでいます。
認知症に悩む方々の良き相談者となれるように、一つ一つの関わりを大切に学びにしていきたいと思っています。
-
有田 沙也加 SAYAKA ARITA
急速な超高齢化に伴い、認知症の人も増加しています。認知症看護認定看護師には、認知症であっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた環境で生活することができるよう支援する役割があります。
私は病棟に所属し、認知症サポート委員会の一員としても院内の認知症看護の充実に向けて活動しています。認知症の人は、疾患による苦痛や環境変化の影響を受け混乱することが多く、対応が困難となる場合もあります。認知症の人が「ここは安心できる場所」と感じることができる療養環境を目指して、スタッフと共に考え、時には悩みながら実践を積み重ねています。混乱していた認知症の人が本来の姿を取り戻す過程を支援する中で、改めて認知症看護の重要性を実感しています。
認知症の人と共に生きる社会を目指す現在、看護師には幅広い役割が期待されています。認知症の人とご家族、スタッフが笑顔で過ごすことができるよう、自己研鑽に励み、認知症看護における質の向上に努めていきたいと考えています。